ありがたいアウトプットの場 ― 2009年07月04日 21時12分19秒
カルチャーセンターは、長いこと、私の仕事の一部になっています。忙しいときにはやめてしまおうかと思ったりもしますが、平素勉強していることのアウトプットの場だと考えればありがたく、当分続けることになりそうです。
とはいえ、土曜日の午前中の出勤は、毎度自分を鼓舞して、という感じになります。遅れてはいけないとバス停からタクシーに乗り、国立駅へ。10円がないのを誤りながら千円札を出そうとしたら、財布がありません。タクシーを自宅まで返して財布を取り、再び国立駅へ。だいぶ遅れてしまいそうです。カルチャーに遅れるのは具合が悪いなあ、と思っていたら、中央線がすぐ来て三鷹で特快に乗り換え、時間に着くことができました。今日も、ツキを使いすぎた始まりです。
「新・魂のエヴァンゲリスト」の講座は、小さな教室がほぼ満員、という感じで進めています。混んでいるな、と思って見回すと、空いているのが、私の目の前の席だけ。やっぱり、にらめっこは避けたいですものね。ところが、遅れてきた方が気の毒にもその席に着かれ、満員に。その後さらに来られた方があり、補助席が出されました。ここに来て受講生が増えているのはありがたく、当然、気合いが入ります。
今日は、《ヨハネ》《マタイ》両受難曲をつなぐ時期がテーマでした。バッハが教会カンタータを毎週のように書き綴っていた頃です。主要なカンタータを少しずつ聴きながら進めたのですが、やはり、この時期こそバッハの絶頂期だと実感。中でも1724年の9月から11月にかけての2ヶ月には、私がカンタータ10選を選ぶとしたら必ず入れるであろうBWV78、8、26が集まっているのです。いわゆるコラール・カンタータの、すばらしい高まりの時期です。
終わったあと、2人の方から、《マタイ受難曲》公演に感動した旨のお話しをいただきました。うち1人の方は両方を聞かれ、私の著作も精読してくださっているとか。こういう方々のためにももっと勉強し、アウトプットもしていかなければ、と思いました。考えてみれば、カルチャーなどでのレクチャーの積み重ねから、今回の《マタイ受難曲》の企画も、聴衆も生まれてきているわけです。ちょっと嬉しくなり、帰路ヨドバシカメラで、ゲームを2つ買ってしまいました(笑)。
新著できました ― 2009年01月19日 20時36分56秒

今日、私の新著『バッハ/カンタータの森を歩む3 ザクセン選帝侯家のための祝賀音楽/追悼音楽』(東京書籍)ができあがってきました。解説されているのはBWV193a、198、205a、206、207a、213、214、215、Anh.9、Anh.11、Anh.12、Anh.13の12曲で、BWV213(ヘラクレス・カンタータ)のCDがついています。演奏は、バッハ・コンチェルティーノ大阪です。値段はちょっと上がって、3,800円になりました。
帯の裏面に、「あとがき」からの1節が引用されています。ここでもそれを引用しておきましょう。「バッハは、ライプツィヒ時代(1723-50)の27年間、ザクセン選帝侯国の住民であった。バッハの領主はヴェッティン家の選帝侯であり、選帝侯は同時に、ポーランド王であった。したがってバッハは、事実上ポーランド国民でもあったことになる。ザクセン選帝侯=ポーランド国王とその一家のためのカンタータは、祝賀のにぎやかな式典に演奏されたり、記念日にコーヒー店で演奏されたりした。それらは、教会の礼拝を目的とした教会カンタータ群とは、まったく異なった環境で鳴り響いたのである。このため本巻の研究も、バッハの時代における政治や国際関係、社会や風土の歴史に注意を払いながら進められた。これは私にとって新しい課題であったから、私は研究を通じて多くのことを学び、しばしば、目からうろこの落ちる思いがした。そこから見えてきたのは、バッハにおける聖と俗の深い、密接なかかわりであった。」
万全を期したつもりでも、間違いは、手に取ったとたんに判明するものです。今収録作品を写していて、BWV193aとあるべきところが、表紙でAnh.193aとなっていることを発見。それは仕方がないですが、「あとがき」でCDの録音場所を「いずみホール」と記しているのは重大な記憶違いでした。巻末のデータにある通り、「相模湖交流センター」が正解です(柴田さん、ごめんなさい)。いきなりこれじゃ、宣伝になりませんね。でも、買ってください(笑)。
世俗カンタータ論脱稿 ― 2008年12月11日 23時48分16秒
今日もたくさん仕事をしました。私の場合「たくさん」と言えるかどうかのバロメーターは、夜ビールを飲んでいるときにもまだ仕事をしているかどうか、ということです。ここ数日していますので、こういうときには、「自分をほめてあげたい」という気持ちになります。
急いでいる仕事をいくつも並行して進めているのですが、今日で一応メドが付いたのは、「ザクセン選帝侯家のための祝賀/追悼カンタータ」の本。私の声楽曲研究はこれまで宗教音楽に偏り、私なりの聖書研究/キリスト教研究と組み合わせて行われてきました。しかし今回初めて世俗カンタータと取り組み、当時の歴史、社会、政治とからめる形で調べを進めました。新しい知識がたくさん広がったと感じています。リレー式で書いている総論のテーマは、「バッハとドレスデン」です。
198番、205番a、206番、207番a、213番、214番、215番を採り上げましたが、音楽が失われ台本のみ残っている数曲についても、かなり頁数を費やしました。それらにも、時代との密接な関連が見られるからです。まだ発売日は決まっていませんが、手にとっていただければ幸いです。CDとしては、バッハ・コンチェルティーノ大阪の演奏した213番が付いています。
考えすぎ? ― 2008年08月20日 22時42分44秒
バッハのカンタータも、少しずつDVDが出るようになってきました。コープマンのものは6曲収録されていて、古楽様式の洗練された演奏を愉しむことができます。その第106番を鑑賞していて、驚きました。
中間部の合唱曲のフーガに続いて、ソプラノのソロが出てきますね。感動的なところです。その部分の字幕の訳が、「イエスよ 導きたまえ。イエスよ 我を迎えたまえ」となっている。ドイツ語の原文は "Ja, komm, Herr Jesu!"で、直訳すると「そうです、来てください、主イエスよ」となるところです。この単純な文章を、字幕の訳者(名前が出ていません)は大いに工夫し、2つの文章に分けて「意訳」したわけです。
訳者は多分、前の合唱歌詞とのつながりを考えたのでしょう。前の歌詞は、「古い契約にこうある。人よ、汝は死ぬ定めなり、と」というものです。それに対して「そうです、主イエスよ、来てください」ではつながらないと考え、上記の訳を工夫されたのだと思います。しかしkommという動詞をこう訳すことは、私にはとうてい思いつきません。
ここは、「そうです、来てください」でなくてはいけないのです。なぜならこれは、『ヨハネ黙示録』の最後の部分からの引用であり、イエスの再臨への呼びかけにほかならないからです。この部分の感動は、聖書とのこうした響き合いにあると、私は確信しています。
学生の頃、聖書の引用を踏まえたテキストを訳す場合、流布している訳文を用いなければいけないかどうか、議論したことがありました。そのときは結論が出なかったと思いますが、やはり基本は、踏まえなくてはならないと思います。この場合のように、直接の引用である場合にはなおさらです。
とはいえ、一般の訳をそのまま当てておけばいい、というわけではありません。たとえば、ヴルガータ訳ラテン語の文章はふつうの聖書とは大幅に異なっていますから、なるべくラテン語を直訳した方がいい、というのが私の考えです。それはある程度、ルター訳ドイツ後にもあてはまります。
さて、「そうです、来てください、イエスよ」ではなんとなくつながりが悪い、と思うこと自体が間違っているわけではありません。106番の歌詞の中心部はオレアーリウスの祈りの本から取られているのですが、そこでは「死ぬ定めなり」と「そうです、来てください」の間に、「私はこの世を去り、キリストのもとにいたいと願っている」という、フィリピの信徒への手紙の一節が挿入されていたのです。バッハは、それを省略した。ですから、タネ本では「キリストのもとにいたい」を受けていた「そうです」が、死の定めを肯定するものに代わりました。
バッハがなぜその一文を省略したかについては別途考察が必要ですが、結果として、死の定めが肯定され、イエスの再臨が待望される、という流れになっていることは確かです。そしてそのことはとても大切であると、私は思います。
BWV106に画期的な新説登場 ― 2008年03月20日 22時37分29秒
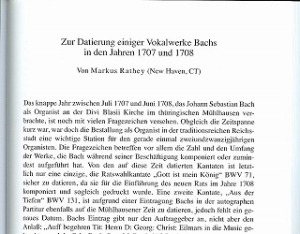
カンタータ第106番《神の時は最良の時》は、多くのバッハ・ファンが、愛してやまない曲。私も昨年相模大野で、マニアックな「徹底研究」コンサートを開きました。その成立事情に関するマルクス・ラタイの画期的な新説が、『バッハ年鑑Bach-Jahrbuch 2006』に発表されました。
「アクトゥス・トラギクス」(哀悼の式)と副題されるこのカンタータが、何らかの葬儀に演奏されたことは確実です。でもそれが誰の葬儀かについては、いくつかの薄弱な仮説があるのみでした。ラタイはそれを、ミュールハウゼンの市長、アードルフ・シュトレッカーAdolph Streckerの葬儀であるとします。シュトレッカーは1708年9月13日に84歳で亡くなり、16日に埋葬されました。同年2月14日に初演された市参事会員交代式用カンタータ《神は私の王》BWV71には80歳の老人への言及がありますが、それはこのシュトレッカーを念頭に置いたものだと、すでにメラメドが指摘しています。
シュトレッカーはとりわけ信仰深い人で、BWV106の出典となっているオレアーリウスの著作や神学思想に親しんだ世代に属していました。彼はかなり長い闘病の期間に、ルターの教えによりつつ死に備えることを学び、現世の苦しみと神の栄光の永遠を対比して、そのテーマによる追悼説教を望んでいたそうです。
追悼説教を行ったのはフローネ牧師(バッハの上司)で、そのタイトルは「時(Zeit)と永遠における真のキリスト者たちの救い」というものでした。これは、「神の時」という台本の冒頭(出所不明)と響き合っていますし、フローネの説教全体も、カンタータの思想と響き合っていると、ラタイは指摘します。1708年9月というとバッハはもうワイマールに移っていましたが、ミュールハウゼンとの音楽的かかわりは続いていましたので、不都合はありません。今後、通説化されるに違いない卓見だと思います。
最近のコメント