カウンドダウン9--学会講演 ― 2009年06月05日 23時53分47秒
今日は18:00より、日本音楽学会関東支部の特別例会として、リフキン先生の講演会が行われました。演題は既報の通り、「バッハの苦闘、私の苦闘--《ロ短調ミサ曲》校訂記」というものです。
来日後たくさん消化すべき予定の内で、私がもっとも大きな山と思っていたのが、今日の講演でした。それは、私が司会のみならず不得意の英語の通訳をしなければならないという、個人的な事情によります。学会ですから、公演終了後の質疑応答は通訳なしのフリー・ディスカッションにしてもらっていたのですが、それがしっかり機能するかどうかはわかりませんでしたので、気の重いハードルとして、今夜が存在していました。
講演は、区切りごとに通訳を入れる形で、1時間半にわたり、ぴしっと進行。ハードワークではありましたが、無難に進み、最後の部分は感動的でさえありました。先生のお薦めをいただきましたので、どこかに発表できればと思います。
残り25分の段階で、ほぼ満員のフロアに、質疑応答を振りました。最初の質問が出るまでに時間がかかりましたが、口火が切られると次々と手が上がり、充実のディスカッション。やはり講演の正否を決めるのはフロアからの質問ですね。
驚いたのは、会員、一部非会員の方々の語学力です。英語とドイツ語が半分半分でしたが、そろって流暢に、意を尽くした質問をされます。それをリフキン先生が丁寧に、わかりやすくお答えになるので、通訳なしでも充分に意思疎通の図れる形で、議論を全うできました。今日は本当に、会員の方々のお力に支えられた会でした。
上野で回転寿司を食べ、先生をホテルまでお送りして帰宅。疲れましたが、充実感が残っています。
カウントダウン15--学会講演のあらまし ― 2009年05月30日 23時14分12秒
今日はまとめて時間が取れましたので、リフキン先生が学会でされる講演「バッハの苦闘、私の苦闘--《ロ短調ミサ曲》校訂記」の翻訳を作りました。その過程で、ブライトコプフの新校訂版とファクシミリ版の比較などもしてみましたが、先生のお仕事の専門性の高さと詳細さに、ほとほと感嘆しています。
講演はまず、美術評論家ロバート・ヒューズの引用から始まります。超越的な存在として畏敬の対象となっているバッハと《ロ短調ミサ曲》も、知られざる弱さを克服しての苦闘を通じて生み出された、との趣旨です。
第1章では、1733年の前半部と1748-50年の後半部の筆跡が比較され、バッハの陥っていた身体疾患について新しい見解が示されます。バッハがすでに統御能力を失いはじめていた兆候があることも、指摘されます。
第2章では、筆写や転用によって《ロ短調ミサ曲》が完成されていくプロセスが追究されます。〈サンクトゥス〉の筆写にも興味深い仮説が示され、強い意志で貫かれた記念碑が、傷跡もなまなましくできあがってゆくさまが語られます。
第3章は、エマーヌエルが父の〈ニケーア信経〉に対して行った修正や書き込みの詳論です。これはまさに、昨年10月の学会シンポジウムで議論された問題と重なり合っています。これには、校訂出版の歴史が続きます。
第4章は、自らの校訂の苦心談です。有名な1981年のレコーディングの時点ですでに新版の基礎はできており、それがその後の作業によって大きく変化していったことがわかります。
訳していて、本当に勉強になりました。ぜひ、聞きにおいでください。5日金曜日18時から、芸大です。
復活楽章の出典(2) ― 2008年05月05日 22時23分45秒
選帝侯誕生日祝賀カンタータの冒頭歌詞は、"ENtfernet euch, ihr heitern Sterne! "(遠ざかれ、明るい星たちよ!)と始まります。ヘーフナーは、復活の主題にターン音型(バロックの修辞学的音楽論に言う旋回Circulatioフィグーラ)が使われていることに注目し、それが原歌詞の「星」という語のイメージに由来すると考えました。「星」を旋回音型で表現する例として、彼はシュッツの《クリスマス物語》を挙げています(第4インテルメディウム)。
しかし、復活の主題に上記のドイツ語歌詞を振ってみると、旋回音型にはeuchの語が当たってしまいます。修辞学的音楽論では語と音型が直接に対応するのが原則ですから、祝賀カンタータの冒頭楽曲から《ロ短調ミサ曲》の復活楽章が作られたとする説の根拠としてこのフィグーラの存在を挙げるのは、適切とは思えません。
より重要なのは、それによって長大唐突なバス・ソロへの説明がつくかどうか、です。ドイツ語歌詞(後半)を振ってみると、語反復の工夫によって、それなりに形はできます。しかしバスは楽章の中間部ですでに何度か歌われた歌詞を歌い直す形になり、なぜ突然バス・ソロか、という問題が残ってしまいます。
復活楽章のテキストは、主部が復活の報告、中間部が昇天の報告となっており、中間部の終わり、バス・ソロの部分で、再臨・審判の預言に移ります。そして、統治の永遠を語る最後の行が、再現部を構成する。すなわち、バス・ソロ(キリストの声?)を驚きの効果を踏まえて投入することに、十分な根拠があるわけです。
ですから、バッハが何らかの楽章をもとにして復活楽章を作ったと仮定するにしても、バス・ソロの部分は、〈クレド〉の当該歌詞を効果的にさばくために新たに挿入した、と見る方が、理にかなっているのではないでしょうか。そうした補正はパロディの場合よく行われますので、現在見る形に原歌詞をそのまま当てはめられるとは限りません。
以上2つの理由から、ヘーフナーの説は成り立たない、というのが私の結論です。・・こう書いても、説明不足で何のことかわかりませんよね。ちゃんとした記述は、次の著作をお待ち下さい。『カンタータの森』シリーズの第3巻として、ザクセン選帝侯関連の世俗カンタータを集めた1冊を準備しています。いろいろ新しい情報を盛り込みますが、昨今の多忙で、執筆が遅れています。
復活楽章の出典(1) ― 2008年05月04日 22時05分57秒
今日は、ちょっと専門的な情報提供です。
《ロ短調ミサ曲》の諸楽曲が、とくにその後半においてしばしば既成楽曲からの歌詞を振り直した転用(パロディ)であることは、よく知られています。原曲がわかっている曲もいくつかあるが、わからない曲もある。特に謎めいているのが、〈クレド〉の中程にある復活楽曲(〈そして三日目によみがえりEt resurrexit tertia die〉)です。トランペットの鳴り渡る生気にあふれた楽章で、《ロ短調ミサ曲》最大の聴き所のひとつですね。
これがパロディであろうというのは、バッハ研究において根強く言われてきたことでした。途中、〈そして栄光に満ちてふたたび到来し、生者と死者を裁かれるでしょう et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos〉のくだりで突然、バスのソロがあらわれます。私も大学の合唱団で歌ったことがありますが、とても歌いにくく、不自然にも感じられる部分です。これに原曲があり、別の歌詞が振られていたとすれば、なるほどそれなら、となる可能性があります。
1977年の『バッハ年鑑』にクラウス・ヘーフナーが、この楽章の原曲は、失われた世俗カンタータ《遠ざかれ、明るい星たちよ》BWVAnh.9の冒頭合唱曲である、とする説を発表しました。このカンタータは、先代のザクセン選帝侯、フリードリヒ・アウグスト一世がライプツィヒの見本市を訪れたさい(1727年、《マタイ受難曲》初演直後)に初演された誕生日祝賀作品で、楽譜は失われましたが、バッハの指揮による祝賀演奏を記録した文書に、歌詞が掲載されているのです。
ヘーフナーの説は、シュルツェ/ヴォルフの『バッハ便覧』にも記述され、通説とはいかぬまでも、広く知られるものとなっています。 もしこの説が正しいとすると、あのすばらしい楽曲が選帝侯祝賀のカンタータの冒頭を飾り、市の中央広場で、大々的に演奏されていたことになる。「バッハにおける聖と俗」といった問題を考える上で、避けて通れません。 そこで、ヘーフナーの論文を読み直し、楽譜に歌詞を振って、パロディ説が成立し得るかどうかを、吟味してみました。(続く)
ロ短調学会(11) ― 2008年01月25日 17時04分31秒
「ロ短調学会」への補遺です。
《ロ短調ミサ曲》をめぐる問題のひとつは、この作品をどこまでルター派プロテスタント的なものとみるか、あるいはカトリック的なものとみるかということでした(この問題については、小林義武先生の『バッハ--伝承の謎を追う』(春秋社)に、詳しく論じられています)。もちろんそれが問題になるのは、ルター派の教会音楽家であったバッハが、カトリック的な相貌をもつミサ曲をカトリックの領主に捧げたという、特殊な事情があるからです。曲が畢生の大作であるだけに、ここをどう考えるかは、バッハ像の根本にかかわるわけです。
近年、バッハとドレスデン宮廷の密接な関係が認識されるにつれ、《ロ短調ミサ曲》をカトリック的なものと認める、という考え方が強くなってきていました。この曲の楽譜は、息子C.P.E.バッハの遺産目録に「大カトリック・ミサ曲die grosse catholische Messe」として出てくるのですが、この名称をそのまま使う人もかなり増えている状況でした。
「ロ短調学会」では、ロビン・リーバー氏が《ロ短調ミサ曲》のルター派的性格を改めて述べ、「大カトリック・ミサ曲」という呼称にある「カトリック」とは文字通り「普遍性をもつ」という意味で、ローマ・カトリックを指していない、と強調しました。ヴォルフ氏も同じ見解を述べていましたが、その「カトリック」を「ローマ・カトリック」と峻別することにはやや無理があるのではないか(つまり相当まで重なっているのではないか)と、私は思いました。
バッハの「宮廷作曲家」称号請願の意図や請願書の文章を、バッハが同じ年(1733年)に購入した『カーロフ聖書』から解釈する発表もありました(M.D.グリーア)。総じて、バッハ研究の世界ではプロテスタント系の発想がなお強いようです。この問題に関する私自身の考えについては、稿をあらためて。
ロ短調学会(10) ― 2008年01月12日 20時35分17秒

私は東京生まれなので、大都会の雑踏は好きです。ロンドンは、じつににぎやか。いいところで夕食をし、自分を褒めてあげたいと思ったのですが、結局は三越のレストランで、ワインと冷や奴、という程度になりました。飲みながらつくづく思ったのは、来てよかった、ということです。それも、単なる聴講ではなく、発表をしてよかった。準備もたいへんでしたし、プレッシャーもありましたが、発表をしたからこそ、これだけ勉強になった、と感じています。やはり困難なことにチャレンジすることで、先が開けます。私の年齢でもそうなのですから、若い人たちには、ぜひ、挑戦することの価値を知っていただきたいと思います。今回の成果は、私の力以上に、いろいろな方の協力によって得られたものです。しかしそうした応援をいただけたのも、挑戦したからではないでしょうか。
食後、ロンドンを歩きました。テムズ川の橋の上に立ったのは10時過ぎ、人通りもまれな時刻でしたが、ライトアップされた国会議事堂は圧巻で、こわいぐらい。これが旅行中、一番印象に残る眺めでした。
6日は、朝1時間だけ、ハイドパークを散歩。写真は、そこにいたリスちゃんです。成田着は7日の朝、へとへとでしたが、その夜いずみホールでオルガン・コンサートがありましたので、直接大阪へ。終了後、すばらしい演奏をした好漢、ミヒャエル・シェーンハイト氏と、京橋で祝杯。速射砲のようなドイツ語を深夜まで浴び、翌日は立ち上がれませんでした。
ロ短調学会(9) ― 2008年01月11日 11時51分24秒
司会者から日本の会長だの、著作がどうだのという紹介を受けるに到っては、開き直って、堂々とやるのみです。ペーパーは。4部構成。「日本における《ロ短調ミサ曲》の初演」(昭和6年における日本初演のいきさつ、実際、評価など)、「〈クルツィフィクスス〉の部分初演」(明治23年〔!〕に東京音楽学校の行った演奏をめぐって)、「バッハ受容のさ中で」(紹介記事や作品論をバッハ受容史とからめて概観する章)、「普遍性をめぐる視点」(「普遍性」という視点がどのように形成されたか、またそれが日本人の同曲受容にどのような意味をもつかを論じた章)の順序で、映像なども使いながら、話を進めました。
出来映え、反響は人様の判断すべきことですが、自分としては納得し、満足しています。私の錯覚でなければ、聴き手の方々に、少なからぬ関心と敬意を喚起できたと思います。質疑応答ではさすがに英語が破綻してしまいましたが、今の実力では、それは仕方のないこと。夕食後、達成感にひたりつつ、クロージング・コンサートを聴きました。教会で、John Butt指揮、The Dunedin Consort and Players(小編成のピリオド楽器アンサンブル)による全曲演奏を聴いたのですが、はじけるような生気にあふれていてすばらしく、元気をもらいました。
ふたたび大学へ戻り、富田さん以下スタッフの心づくしを受けて、打ち上げパーティ。われわれ日本人組は途中でホテルに引き上げ、絶品のギネスを飲みながら、さまざまなことを語り合いました。途中鈴木さんも加わり、大いに盛り上がった一夜でした。
ロ短調学会(8) ― 2008年01月10日 14時05分29秒

鈴木さんの知名度は高く、世界を代表するバッハ演奏家として尊敬を受けています。それもあって、休憩中もいろいろな方と積極的に会話されており、声をかけるタイミングがつかめない(笑)。結果として、私と日本人グループを形成したのは、樋口隆一さん、星野宏美さんでした。お二人とも国際的な業績を挙げておられる方ですが、ベルファストまで足を運ばれる熱意には、頭が下がります。
11月4日、最終日のセッションが「演奏」(アンドルー・パロット他)で開始されました。レスポンスは、鈴木雅明さん。お昼の「公開Q&Aセッション」を経て、午後はまず「受容史」(ウルリヒ・ライジンガー他)。最後にとうとう--15時40分から--私の加わるラウンド・テーブルが開始されました。
(写真は外国での上演記録を集めたパンフレットの第1ページ。日本のチラシが冒頭を飾っています。)
ロ短調学会(7) ― 2008年01月09日 12時26分31秒
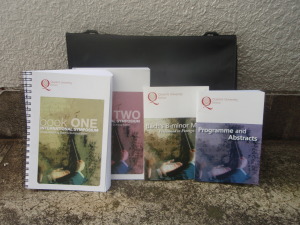
その詳細については機会を改めて報告することにし、先を急ぎましょう。11月3日は、終日、発表と討論が続きました。最初に「神学」のセッション(ロビン・リーバー他)、続いて「作曲と意味(2):数比」(ウルリヒ・ジーゲレ他)、「作曲と意味(1):美学」(ジョージ・スタウファー他)。そして「資料とエディション」(ハンス=ヨアヒム・シュルツェ他)。クリストフ・ヴォルフ氏のキーノート・ペーパー(作品研究の歴史と現状、諸問題に関する要領のよいまとめ)で夕食休憩となり、そのあとはレセプションとなりました。楽しい談笑の写真が公式ホームページに紹介されていますが、私は翌日の発表原稿が不十分だったのでホテルに戻り、改良に精を出しました。深夜、富田さんが訪ねてくださり、疲れもみせずに協力してくださったのには感謝。富田さんの献身的な働きへの賞賛と感謝は、すべての参加者の口に満ちあふれていました。
疾風のように、英語の飛び交う学会です。みんな、ものすごいスピードでしゃべる。指揮者のアンドルー・パロットさんなんか、超特急。不安になった私が長老のジーゲレ先生に「英語ができないので心配です」と申し上げると、「私もですよ」というお返事。たしかにドイツ系の先生には、英語は苦手とお見受けする方が案外おられました。それでも、質問の内容は的確にとらえて、最低限の対応をする。やはり、ヒアリングが一定のレベルにあることが、重要なようです。
(写真は、配布された資料。発表論文を集めた冊子、既存の研究を集めた冊子、プログラムとレジュメ集、諸外国の演奏記録を集めた冊子。)
ロ短調学会(6) ― 2008年01月08日 14時24分52秒

セッションは、全部で9つ。今回の工夫は、2~3人の発表者のあとに「レスポンス」というコーナーが設けられ、その担当者が発表の意義を自分なりにまとめながら質問を投げかけ、それをきっかけに、ディスカッションに入るようになっていたことでした。
たとえば、歴史的背景を幅広く扱うセッションでは、リーダー格のクリストフ・ヴォルフ氏がレスポンスを担当して、主流の立場からの意味づけと、問題点の洗い出しを行う。これはとても、理解の助けになります。
1日目の白眉は、ワルシャワ大学のシモン・パチコフスキ氏の発表でした。《ロ短調ミサ曲》の成立は、ご承知の通り、バッハがドレスデンの宮廷作曲家の称号を、即位したばかりの新ザクセン選帝侯に請願したこととかかわっています。したがって、《ロ短調ミサ曲》を論じるためには、ドレスデンの研究が欠かせません。
しかるに先代のザクセン選帝侯(フリードリヒ・アウグスト1世)はポーランド王を兼ねており、息子の2世がその王位を継承できるかどうかは大問題で、まもなく、国際的な継承戦争が起ったほどでした。したがって、ドレスデンの研究には、ポーランドの研究が欠かせないのです。その意味で期待されるのはポーランドのバッハ研究であるわけですが、従来は言葉の問題もあり、それがあまり紹介されていませんでした。しかしパチコフスキ氏の参加によって、それが興味深い進展を遂げていることが明らかになりました。(続)
最近のコメント